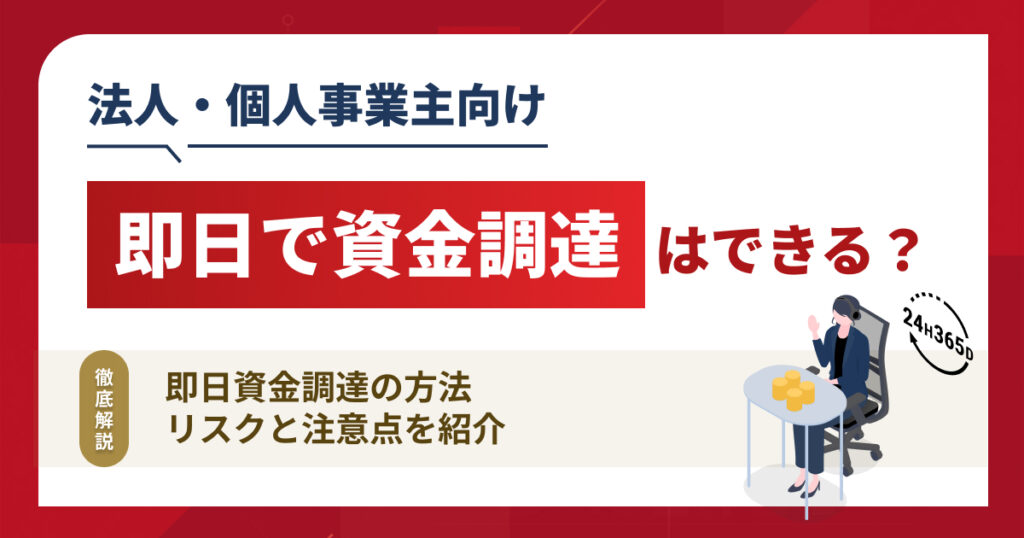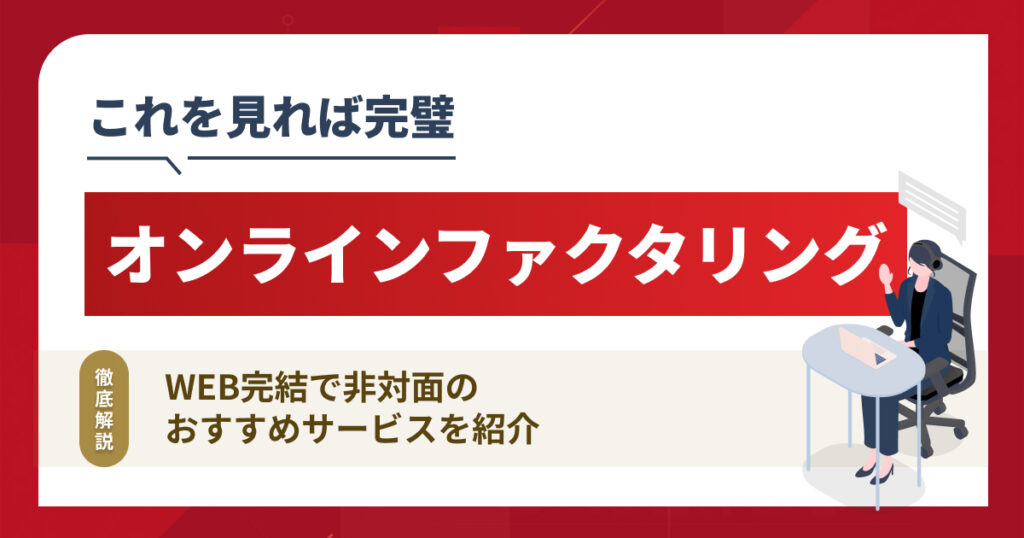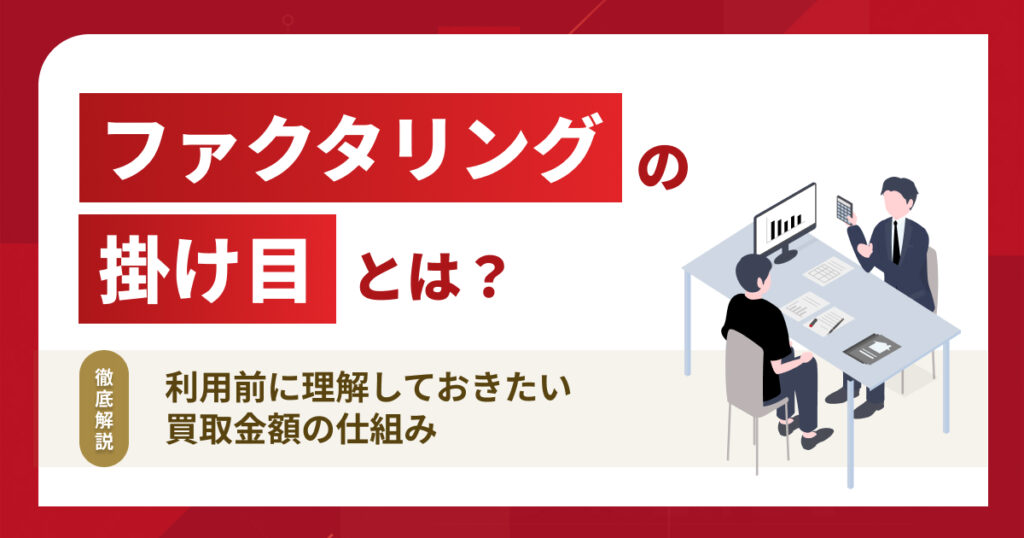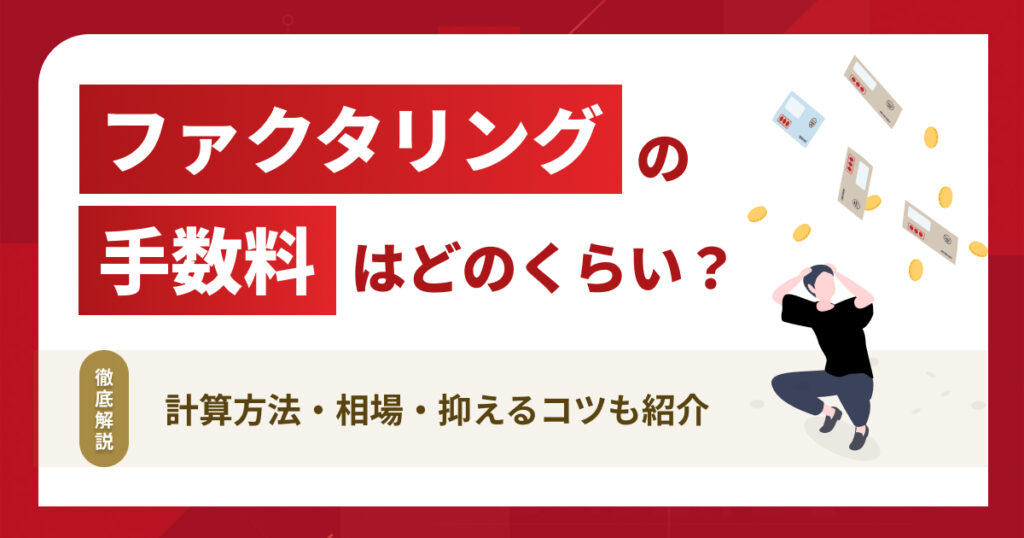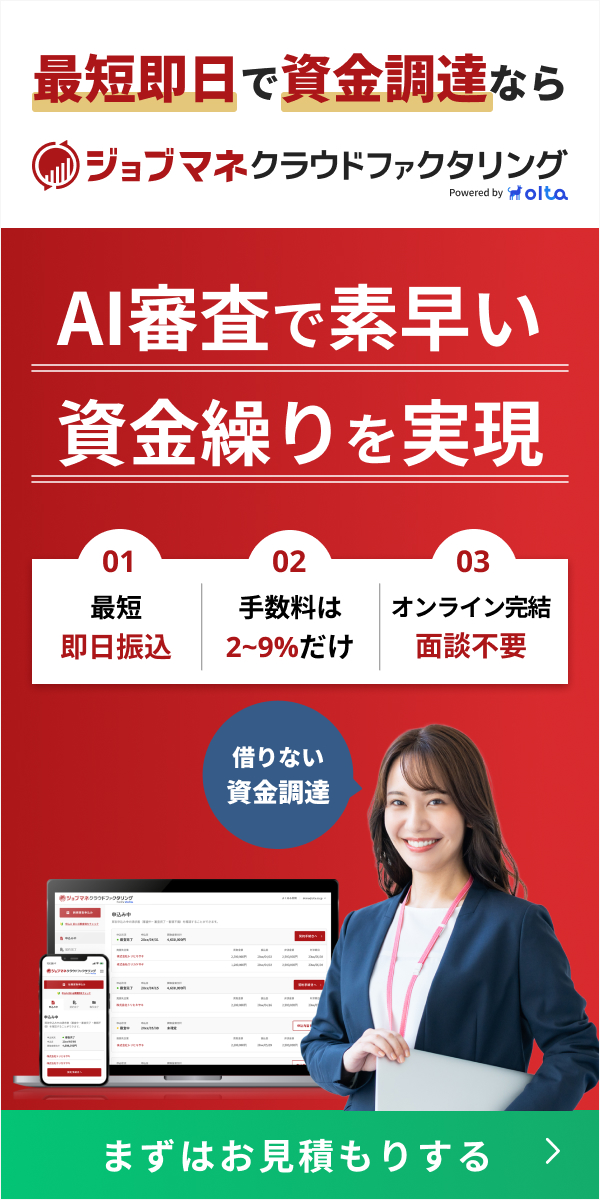注文書ファクタリングとは?メリット・デメリットや請求書買取との違いも解説
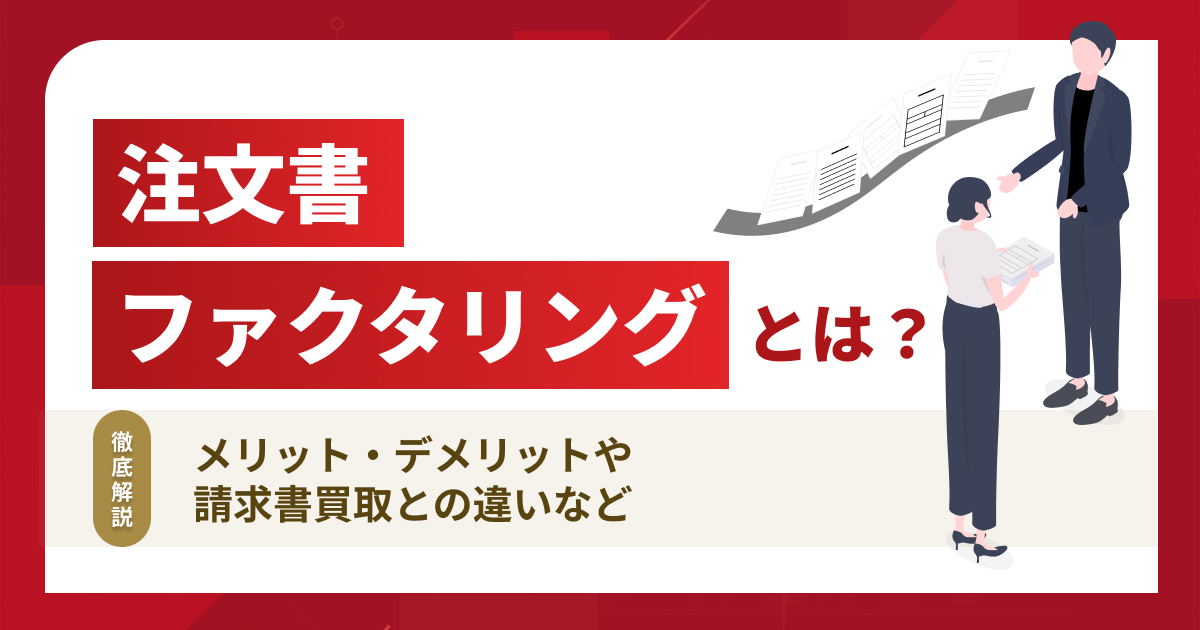
中小企業や個人事業主の資金繰りは常に重要な経営課題です。中小企業庁「中小企業庁 令和6年度(2024年度)中小企業の動向」によれば、多くの中小企業が資金繰りに不安を抱えており、特に創業間もない企業や成長フェーズにある企業ではその傾向が顕著に見られます。
そんな中、従来の銀行融資に代わる新たな資金調達手段として注目されているのが「ファクタリング」です。特に「注文書ファクタリング」は通常のファクタリングよりも早い段階で資金化できるため、急な資金需要に悩む企業の間で関心が高まっています。
本記事では、注文書ファクタリングの仕組みやメリット・デメリット、一般的な請求書ファクタリングとの違いについてわかりやすく解説します。資金繰りに悩む経営者の方々は、新たな選択肢を検討する際の参考としてください。
注文書ファクタリングは請求前に現金化できる資金調達手段
注文書ファクタリングとは、取引先から受け取った発注書や注文書を元に、実際の納品・請求前に売掛金を現金化できる金融サービスです。通常のビジネスでは、商品やサービスを提供した後に請求書を発行し、支払いを受けるまで一定期間待つ必要があります。この待期期間が資金繰りの課題となることは少なくありません。
注文書ファクタリングでは、受注段階(注文書を受け取った段階)で将来の売掛金を担保に資金調達できます。これにより納品前や請求書発行前に現金を手にすることが可能です。材料調達や人件費の支払いなど、ビジネスを進めるために必要な資金をスムーズに確保できる点が魅力といえるでしょう。
仕組みとしては、企業が取引先から注文書を受け取った後、その注文書をファクタリング会社に提示して資金調達を申し込みます。ファクタリング会社が注文内容や取引先の信用力を審査し、審査通過後、注文金額の一部が前払いされます。そして実際に納品・請求・入金が完了した後、残金(手数料を差し引いた額)が支払われる流れとなります。
ファクタリングは中小企業の資金調達手段として一定の利用があり、資金繰り対策の選択肢として認知されているのが現状です。
注文書ファクタリングは特に、大企業との取引がある中小企業や、プロジェクト型のビジネスモデルを持つ企業、季節変動の大きい業種において有効な資金調達手段となっています。ただし、後述するように手数料が比較的高いため、継続的な利用には注意が必要です。
請求書ファクタリングとの主な違いを解説
注文書ファクタリングと請求書ファクタリング(一般的なファクタリング)は、どちらも売掛債権を活用した資金調達手段ですが、いくつかの重要な違いがあります。
請求書ファクタリングは、すでに商品・サービスを納品し、請求書を発行した後の売掛金を買い取ってもらうサービスです。一方、注文書ファクタリングは注文を受けた段階で、まだ実際の納品・請求が行われる前に資金化できる点が最大の違いです。
中小企業庁「中小企業を支える資金調達(2024年版中小企業白書)」によれば、多くの企業がより早い段階での資金化ニーズを持っています。そのニーズに応えるサービスとして注文書ファクタリングは注目を集めているのです。
請求書型よりも早い段階で資金を現金化できる
注文書ファクタリングの最大の特徴は、ビジネスプロセスの早い段階で資金化できる点にあります。一般的なビジネスの流れは、受注(注文書受領)から始まり、商品製造・サービス提供、納品・完了、請求書発行を経て、最終的に支払い(入金)に至ります。請求書ファクタリングは請求書発行から支払いの間で利用できるのに対し、注文書ファクタリングは受注直後に利用可能です。この違いは資金繰りに余裕がない企業や、材料費など前払いが必要な業種にとって大きなメリットとなります。
たとえば、大型の注文を受けたものの、材料調達や人件費の支払いに資金が必要な場合、注文書ファクタリングを利用すれば実際の納品前に必要な資金を確保できます。
日本賃金協会「2024年度資金需要者等の借入意識や借入行動等に関する調査」によれば、多くの中小企業が受注から入金までの期間の資金繰りに苦労しています。この課題解決のための方法として早期資金化手段が検討されている状況です。
請求書型よりも手数料は高くなりやすい
注文書ファクタリングは資金化のタイミングが早い分、リスクが高いため、請求書ファクタリングよりも手数料が高くなる傾向があります。
請求書ファクタリングの場合、すでに商品やサービスの提供が完了し、請求書も発行されているため、取引の実在性や確実性が高いと判断されます。一方、注文書ファクタリングはまだ納品前の段階であり、キャンセルや納期遅延などのリスクが存在します。このリスクを反映して手数料率には明確な差があります。一般的に請求書ファクタリングの手数料率は1~10%程度ですが、注文書ファクタリングでは5~20%程度と高めに設定されていることが多いのが実情です。
手数料は債権額の一部の割合として計算され、売上全体に対する影響は取引規模によります。複数の業者から見積もりを取り、比較検討するとよいでしょう。
2社間取引が中心で取引先に通知せず利用できる
請求書ファクタリングには「3社間ファクタリング」と「2社間ファクタリング」の2種類があります。3社間ファクタリングでは売掛先(支払企業)に債権譲渡通知が必要ですが、2社間ファクタリングでは通知不要です。
注文書ファクタリングは、その性質上、基本的に2社間取引として行われます。つまり、取引はファクタリング会社と資金を調達する企業(売掛企業)の間だけで完結し、注文元の企業(売掛先)には通知されないのが特徴です。
これにより、取引先に資金繰りの状況を知られることなく資金調達が可能となります。また、取引先との関係性に影響を与えず、手続きも比較的シンプル(取引先からの承認や手続きが不要)になるというメリットがあります。
多くのファクタリング利用企業が2社間取引における「取引先に知られずに資金調達できる点」をメリットとして挙げています。特に大企業との取引がある中小企業ではこの点が重要視される傾向にあるのです。
注文書ファクタリングのメリットを3つ紹介
注文書ファクタリングは、特定の状況において非常に有効な資金調達手段です。
ここでは主な3つのメリットについて詳しく解説します。
請求書を待たず受注段階から資金を確保できる
注文書ファクタリングの最大のメリットは、受注直後から資金調達ができる点にあります。通常のビジネスサイクルでは、受注から入金までに数週間から数か月かかることがあります。特に大型の受注があり材料調達や外注費など先行投資が必要な場合や、複数のプロジェクトが同時進行し資金需要が一時的に高まるとき、また季節変動の大きい業種で繁忙期に向けた準備資金が必要な場合など、早期の資金確保が重要になる状況は少なくありません。
現実問題として、多くの中小企業が受注から入金までの期間の資金繰り、キャッシュフローを経営課題と捉えています。その対策として早期資金化のニーズが高まっていることが指摘されているのです。
たとえば、飲食店の厨房設備を製造・設置する企業が大型受注を獲得した場合、材料費や下請け業者への支払いが先行して発生します。注文書ファクタリングを利用すれば、これらの先行費用を円滑に支払い、プロジェクトをスムーズに進行できるという利点があります。
長期案件でも早期資金化により安定運営が可能となる
長期にわたるプロジェクトや納期の長い案件では、完了までの間の資金繰りが大きな課題となります。たとえば、建設業や大型システム開発など、完了まで数か月~1年以上かかるプロジェクトでは、その間の運転資金の確保が重要です。
こうした業務は、中小企業にとって大きなチャンスではありますが、同時にプロジェクト期間内での資金繰りはギリギリの勝負になる場合もあります。
注文書ファクタリングを利用すれば、プロジェクト開始時点で一部の資金を確保できます。これによりプロジェクト進行中の安定した資金繰りが実現可能です。また、追加の人材確保や設備投資など、長期的な視点での経営判断がしやすくなり、複数の長期プロジェクトを並行して受注・進行させることも可能になるでしょう。
取引先に知られず利用でき信用を失わない
資金調達の方法によっては、取引先やメインバンクに自社の資金繰りの状況が知られてしまい、信用に影響を与える可能性があります。大企業との取引では、取引先から「財務状況は大丈夫か」と疑念を持たれることは避けたいものですし、メインバンクからの指摘は一括返済が求められる等につながるリスクもあります。
注文書ファクタリングは基本的に2社間取引のため、取引先に知られることなく資金調達が可能です。これにより取引先との良好な関係を維持できます。また、自社の資金繰り状況を開示する必要がなく、将来の取引にも影響を与えない点が大きな利点といえるでしょう。
特に創業間もない企業や、大企業との取引が中心の企業にとって、注文書ファクタリングが重要な切り札となるのです。
注文書ファクタリングのデメリットについて解説
注文書ファクタリングには多くのメリットがある一方で、いくつかの重要なデメリットも存在します。利用を検討する際には、これらのデメリットもしっかりと理解しておくことが重要です。
それぞれ順に解説します。
審査が厳しく取引先の信用力が強く問われる
注文書ファクタリングは、まだ納品前の段階での資金化となるため、通常のファクタリングよりも審査が厳しい傾向があります。特に取引先(注文元企業)の信用力・支払能力、過去の取引実績や継続的な取引関係の有無、そして注文内容の実現可能性や確実性などが重視されるのが特徴です。
特に取引先の信用力は重要な審査ポイントとなります。注文書ファクタリングでは、最終的に取引先からの支払いが行われることが前提となります。そのため、取引先が大企業や公的機関など信用力の高い組織でなければ、審査に通りにくい場合があるでしょう。
注文書ファクタリングは納品前のリスクが高いため、請求書ファクタリングよりも審査が厳しく、特に取引先の信用力や取引実績が重視されます。審査基準は業者により異なるため、事前確認が必要です。また、初めての取引先や取引実績の少ない企業との取引に関しては、さらに審査のハードルが高くなる点も留意すべきです。
利用コストが高く繰り返し利用には向かない
注文書ファクタリングは、前述の通り請求書ファクタリングよりも手数料が高い傾向にあります。リスクを反映した手数料率は、請求書ファクタリングの1~10%程度に対し、注文書ファクタリングでは5~20%程度と高めに設定されていることが多いのが現状です。このため、繰り返し利用すると資金調達コストが大きく膨らむ可能性があります。
ファクタリングを継続的に利用している企業の多くが「コストの高さ」を課題として挙げています。特に注文書ファクタリングではその傾向が強いことが指摘されているのです。
このため、注文書ファクタリングは一時的な資金需要や特定の大型案件に対する臨時の資金調達手段として活用するのが賢明です。継続的な資金繰り対策としては、より低コストの融資や補助金など他の選択肢も検討すべきでしょう。
利用できる業者が少なく選択肢が限られている
請求書ファクタリングに比べて、注文書ファクタリングを提供している業者は限られています。これは、注文書ファクタリングがより高いリスクを伴うサービスであるためです。
市場には多くのファクタリング業者が存在しますが、そのうち注文書ファクタリングを提供しているのは一部に限られており、選択肢が少ない状況といえます。このため、業者間の比較検討が難しく条件交渉の余地が限られます。また、特定の業種や取引形態に対応していない場合がある点や、大手企業との取引に特化している業者が多く中小企業間取引では利用しにくい点などの課題が生じる可能性もあるのです。
一般的に、注文書ファクタリングは請求書ファクタリングに比べ提供業者が少なく、選択肢が限られる傾向があります。業者選定の際は、金融庁への登録状況や実績、評判を確認することが重要です。
また、近年は悪質なファクタリング業者の存在も問題となっています。金融庁は特設ページで注意喚起を行っており、業者選定の際には実績や評判、金融庁への登録状況などを十分に確認することが重要です。
注文書ファクタリングに関するよくある質問
注文書ファクタリングと注文書担保融資はどう違いますか?
注文書ファクタリングと注文書担保融資は、どちらも注文書を活用した資金調達方法ですが、仕組みや特性に重要な違いがあります。
注文書ファクタリングは、将来発生する売掛債権を「買取」してもらうサービスです。つまり、債権自体をファクタリング会社に譲渡(売却)する形になります。一方、注文書担保融資は、注文書を「担保」として金融機関から「融資」を受ける方法です。債権自体は譲渡せず、返済義務のある借入金を得ることになります。
性質の違いとしては、ファクタリングは債権譲渡(売買取引)である一方、担保融資は借入(金融取引)です。また返済義務については、ファクタリングには原則として返済義務がない(ノンリコース型の場合)のに対し、融資には返済義務があります。利用可能性についても、担保融資は主に銀行などの金融機関が提供し審査基準が厳格で財務状況も重視されます。一方、ファクタリングは専門業者が提供し取引先の信用力を重視する傾向があるのが特徴です。さらにコスト面では、一般的に融資の方が金利が低く、ファクタリングは手数料が高い傾向にあります。
資金需要の性質や自社の財務状況、取引先との関係性などを考慮し、適切な方法を選択することが重要といえるでしょう。
注文書ファクタリングはどの業種で特に利用されていますか?
注文書ファクタリングは、特定の業種や事業特性を持つ企業で多く利用されています。
建設業・工事業では、大型の建設プロジェクトや工事案件を受注したとき、資材調達や下請け業者への支払いなど、工事着手前に多額の資金が必要となるケースが多いです。このため注文書ファクタリングの利用が見られます。
製造業においても、特に受注生産型の製造業では、注文を受けてから製品を製造するため、材料費や人件費などの先行投資が必要となります。大型の受注を獲得したときに注文書ファクタリングを活用することで、生産資金を確保しているのです。
IT・システム開発業界では、大規模なシステム開発プロジェクトを受注したとき、開発人員の確保や外注費など、プロジェクト開始時点で多くのコストが発生します。また、開発期間が長期にわたることも多く、その間の資金繰りを安定させるために注文書ファクタリングが利用されています。
イベント・広告業界も、大型イベントやキャンペーンを受注したとき、会場費や制作費などの先行支出が必要となるため、注文書ファクタリングの活用事例が見られるのが特徴です。
また、業種を問わず、大企業や官公庁との取引がある中小企業では、取引先の信用力が高く審査に通りやすいため、注文書ファクタリングの利用が比較的容易となっているのです。
注文書ファクタリングを利用できる会社の条件はありますか?
注文書ファクタリングを利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件はファクタリング会社によって多少異なりますが、一般的には以下のような要件が挙げられます。
まず最も重要なのは、信用力の高い取引先からの注文書を持っていることです。注文書ファクタリングは、取引先(注文元企業)の支払能力に依存します。そのため、取引先が大企業や上場企業、官公庁など、財務的に安定した組織であることが求められます。中小企業同士の取引では、審査が厳しくなる傾向があるのが実情です。
また、取引実績も重要な要素となります。同じ取引先と継続的な取引関係があり、過去に複数回の取引実績がある場合、注文書ファクタリングが利用しやすくなります。初めての取引先からの注文書では、審査が通りにくい場合が多いでしょう。
事業の安定性も審査ポイントです。ファクタリング会社は申込企業自体の事業継続性も評価します。創業間もない企業や財務状況が不安定な企業は審査が厳しくなる可能性があります。ただし、請求書ファクタリングほど厳しくはなく、取引先の信用力が高ければ、比較的新しい企業でも利用できる場合があるのが特徴です。
注文内容の実現可能性も重要です。受注した内容を確実に履行できる能力があるかどうかも審査されます。過去に類似の案件を成功させた実績があると、審査が通りやすくなる傾向にあります。
ファクタリング会社の審査基準によれば、注文書ファクタリングの審査では特に取引先の信用力が重視されます。次いで過去の取引実績、申込企業の事業安定性、注文内容の実現可能性などが総合的に判断されているのです。
最低取引金額については、ファクタリング会社によって異なりますが、一般的には50万円~100万円以上の注文書が対象となることが多いでしょう。小規模な注文では、審査コストに見合わないため、対象外となる場合があります。
利用にあたっては、複数のファクタリング会社に相談し、自社の状況に最も適した条件を提示する業者を選ぶことが重要です。また、悪質な業者も存在するため、金融庁への登録状況や実績、評判などを十分に確認することをお勧めします。