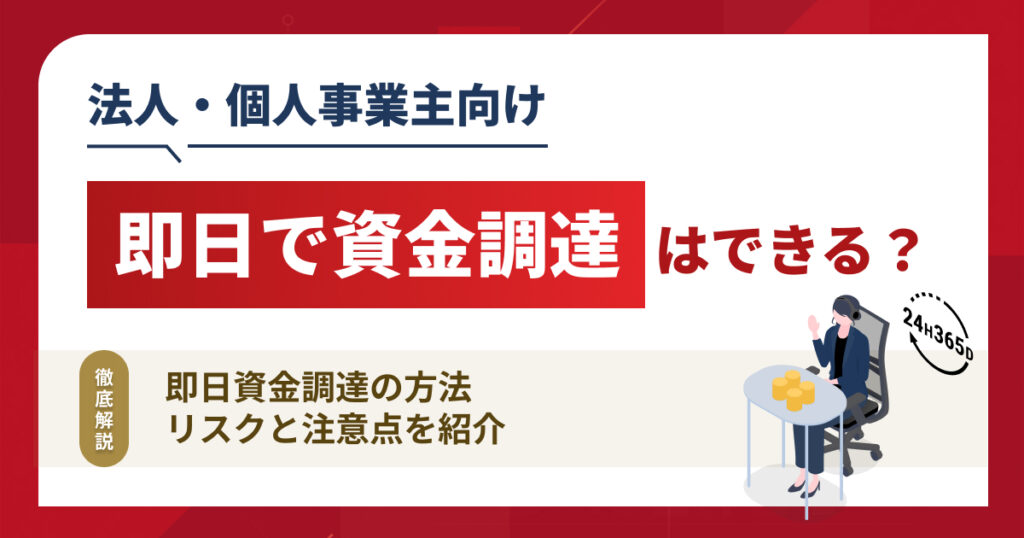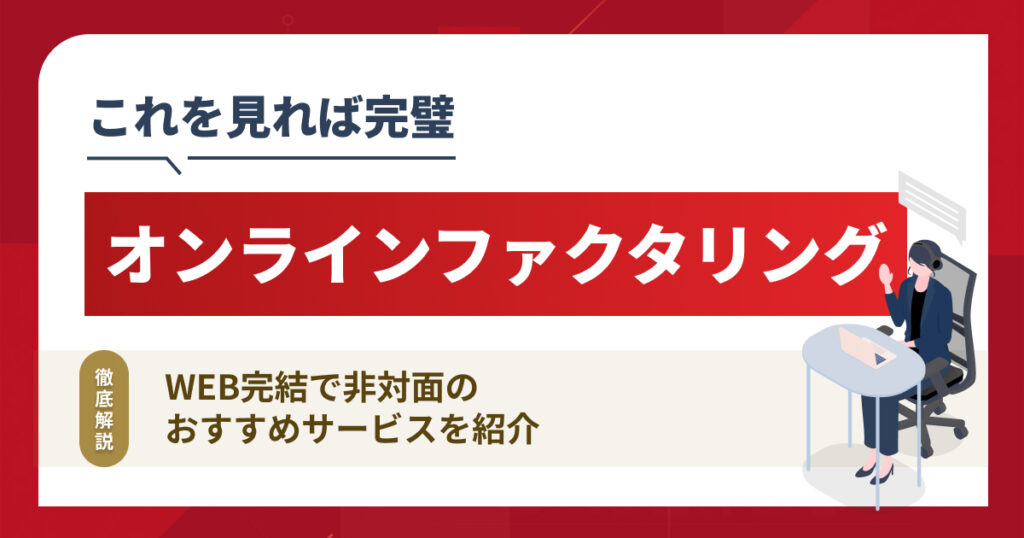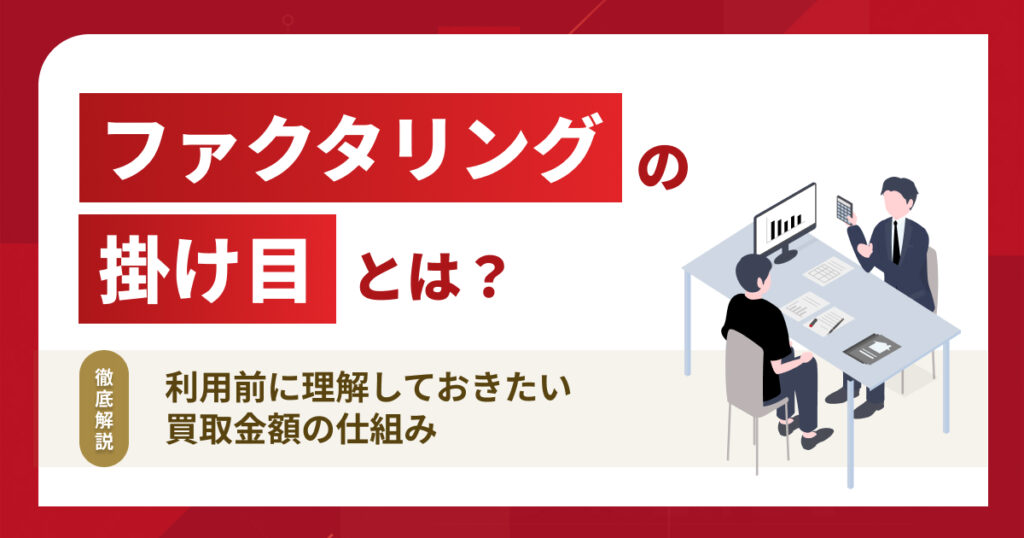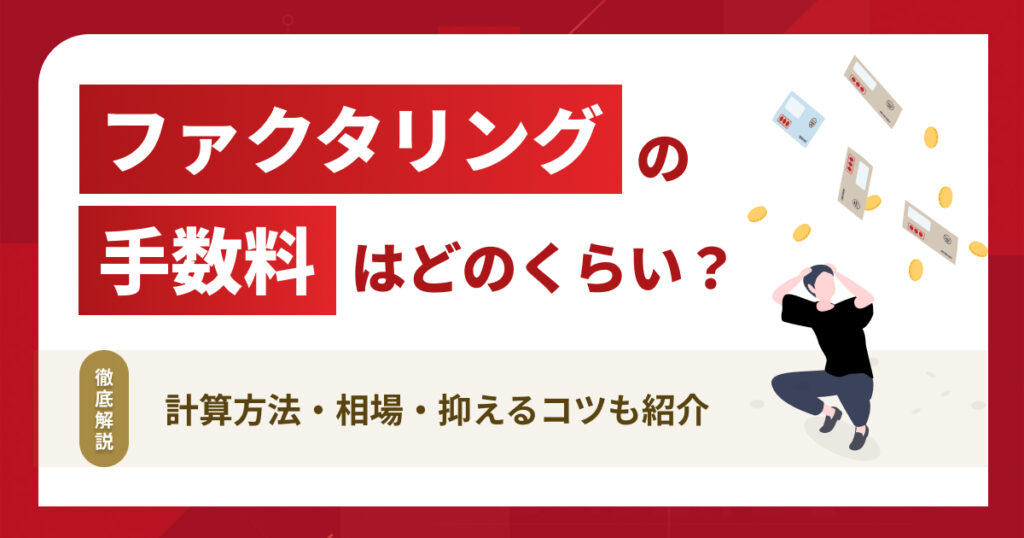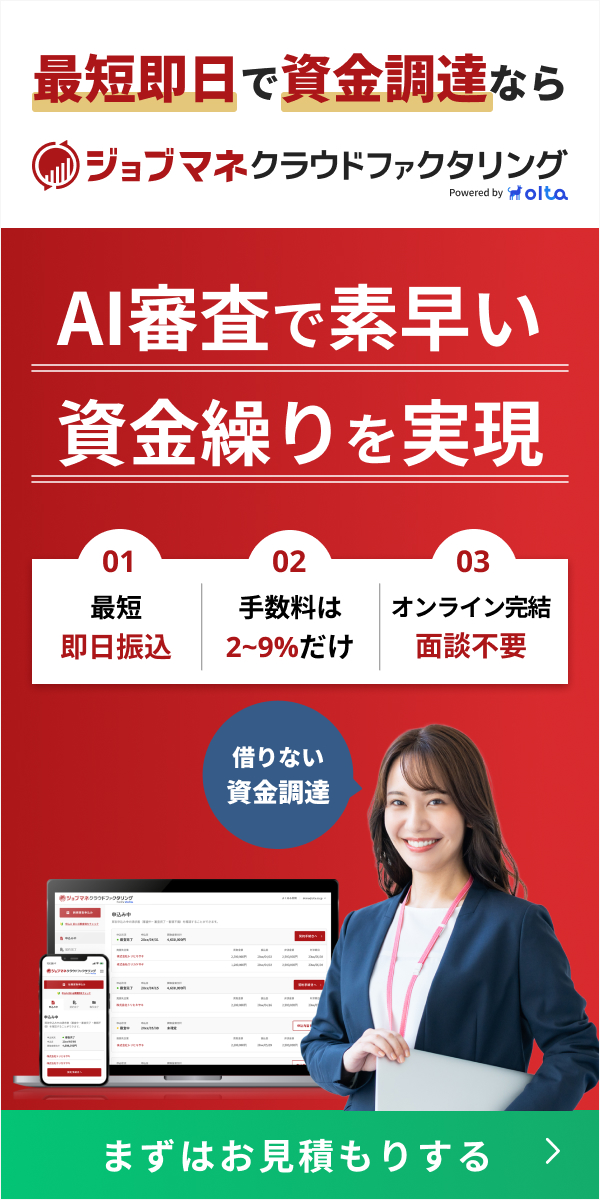期日現金とは?メリット・デメリットや仕組みを解説
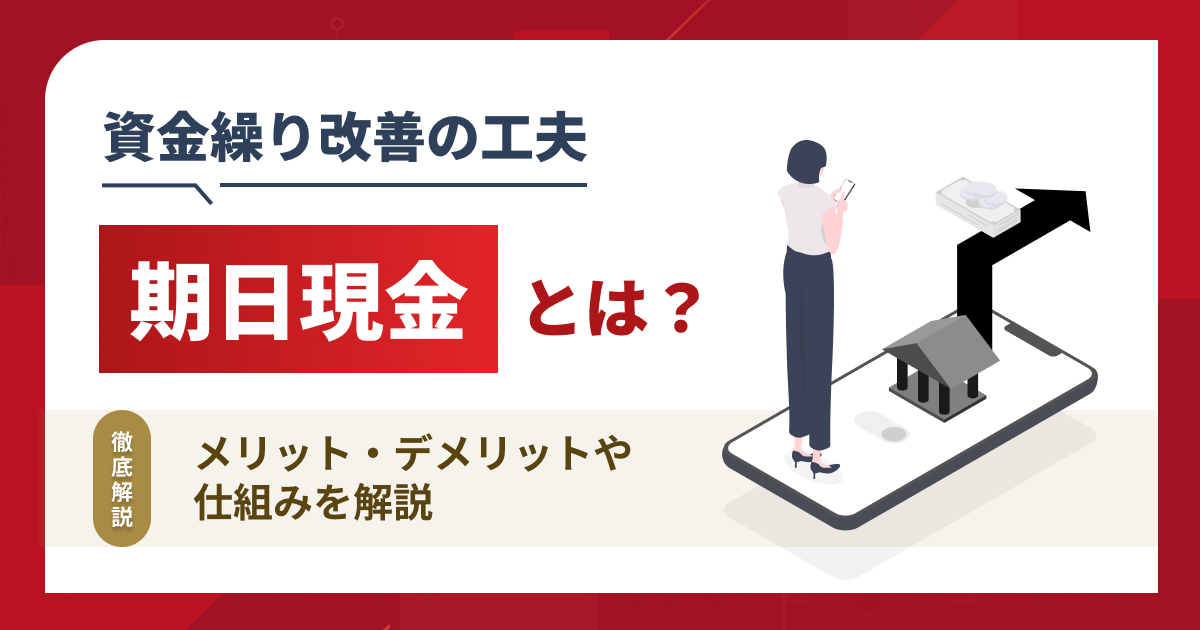
企業間取引においてよく耳にする期日現金という支払条件は、手形や振込など他の決済方法と並んで広く利用されている仕組みです。期日現金とは、売掛金の支払期日を通常より長く設定し、その期日に現金で支払われる決済方法を指し、中小企業や下請取引の現場で多く採用されています。
手形のように証券を発行する必要がなく、比較的シンプルな取引形態である一方、支払サイトや入金までの期間によっては資金繰りに影響を与えることもあります。また、下請代金支払遅延等防止法(下請法)との関わりや、会計処理の方法も知っておくべき重要なポイントです。
本記事では、期日現金の仕組みやメリット・デメリットを解説しつつ、実務での注意点や資金繰り改善の工夫についても詳しく紹介します。
期日現金とは決められた期日に現金振込で支払うこと
期日現金とは、企業間取引であらかじめ定めた期日に代金を現金振込によって決済する方法を指します。小切手や手形のように証券を発行する必要がないため、比較的シンプルで透明性の高い支払い方法として多くの取引で利用されています。
通常は「月末締め、翌月末払い」や「20日締め、翌々月10日払い」といった条件で合意され、これに基づき買掛金が支払われます。起算日や支払サイトの設定が資金繰りに大きな影響を与えるため、双方が納得できる条件を契約書などで明確にしておくことが重要です。また、下請法(下請代金支払遅延等防止法)では支払期日に関する規制が定められており、過度に長いサイトの設定は法的に制限される場合があるため注意が必要です。
それぞれ順に解説します。
期日現金における起算日と支払サイトの扱い方を解説
期日現金取引では、支払い期日をどの時点から数えるかを明確にする必要があります。ここで重要となるのが起算日と支払サイトです。起算日とは決められた期日に代金を現金で支払うこと、また通常よりも支払期日を後ろにして取引することを指し、通常は納品日や検収日、または月末締め日などが設定されます。
一方、支払サイトはその起算日から実際の支払日までの期間を意味し、翌月末払い(サイト30日)や翌々月末払い(サイト60日)といった形で表現されます。この支払サイトの長さによって売掛金の回収までの期間が決まり、資金繰りやキャッシュフローに直結するため、企業にとっては非常に重要な管理項目です。
下請取引では、親事業者が下請法の規制を受けるため、120日を超えるような過度に長期の支払サイトは認められないケースがあります。
起算日の数え方と締め日の関係
期日現金における起算日は、実務上納品日基準・検収日基準・月末締め基準などが用いられます。例えば「月末締め、翌月末払い」という条件では、1か月間に発生した取引を月末で区切り、その翌月末を支払期日とするため、最大で約60日後に代金が入金される形です。
対して納品日基準であれば、納品日ごとに起算日が設定されるため、入金までの期間が取引ごとに異なります。どの基準を採用するかは業界慣行や取引先との契約内容によって変わりますが、いずれにしても締め日と起算日の関係を明確にすることが、資金繰り計画を正確に立てるうえで欠かせません。
また、契約時には口頭での取り決めではなく、必ず書面や契約書で確認することが望まれます。
支払サイトが長期化する場合の注意点
支払サイトが長期化すると、売掛金の回収までの期間が延び、資金繰りに大きな負担がかかります。特に中小企業や下請業者にとっては、仕入れや人件費など先行する支出を自己資金で賄わなければならず、運転資金不足に陥るリスクが高まります。
また、長期サイトは与信リスクも大きく、取引先の経営悪化や倒産により代金が回収できなくなる可能性が高いです。こうした状況を回避するためには、契約時にサイトを必要以上に長く設定しないこと、またはファクタリングなどを活用して早期現金化を図ることが有効です。
さらに、下請法では60日以内の支払が原則とされており、60日を超える設定は下請法違反となり行政処分の対象です。したがって、支払サイトを交渉する際には、法的規制や自社の資金繰り状況を十分考慮する必要があります。
期日現金と手形やでんさいの違い
まず、期日現金・手形・でんさいの違いを以下の表で整理します。
| 期日現金 | 手形決済 | でんさい決済 | |
|---|---|---|---|
| 支払方法 | 振込による現金支払い | 約束手形の発行 | 電子記録債権(電子データ) |
| 証券の有無 | なし | あり(有価証券) | なし(電子記録) |
| 流通性 | なし(譲渡不可) | あり(譲渡・割引可能) | あり(譲渡・割引可能) |
| コスト | 低い(発行・管理不要) | 発行印紙代などコストあり | システム利用料などコストあり |
| リスク | 支払遅延・倒産リスク | 不渡りリスク・管理コスト | システム障害や導入コスト |
| 法的性質 | 金銭消費貸借契約の履行 | 手形法に基づく債権 | 電子記録債権法に基づく債権 |
期日現金は、決められた期日に単純に現金振込で決済される仕組みであり、証券や電子記録を発行しない点が大きな特徴です。一方、手形決済は約束手形という有価証券を発行し、譲渡や割引によって資金化できるため、流動性があるというメリットがあります。
しかし、不渡りのリスクや発行・管理の手間がある点はデメリットです。でんさい決済は、電子記録債権法に基づき発行される電子的な債権で、手形の代替として広がりつつあります。譲渡や割引も可能で利便性が高い一方、システム利用料や導入にかかるコストが発生するのです。
このように、期日現金はシンプルでコストが低いものの流動性がなく、手形・でんさいは資金調達手段として有効ですが、手数料や管理面の負担があります。取引先や業界慣行に応じてどの決済手段を選ぶかを判断しましょう。
手形決済と期日現金の違い
手形決済と期日現金の最大の違いは、手形が有価証券であるのに対し、期日現金は単純な振込による支払いという点です。手形は支払期日までの間に譲渡や割引が可能で、金融機関を通じて資金調達手段として利用できます。つまり、手形には流通性と資金化の仕組みが備わっているのです。
これに対し期日現金は、定められた支払期日まで待たなければ現金化できず、譲渡や割引による資金調達はできません。また、手形は発行にあたり印紙代や管理コストがかかり、不渡りリスクも存在します。
一方、期日現金は管理コストや不渡りリスクがないため、シンプルでコスト負担の少ない決済手段といえるでしょう。中小企業や下請け取引では、近年手形の利用が減少してよりシンプルな期日現金へ移行する動きが広がっていますが、その背景には資金繰りの透明性とリスク低減へのニーズがあります。
でんさい決済と期日現金の違い
でんさい決済は電子記録債権に基づく決済方法で、従来の紙の手形を電子化したものと位置づけられます。でんさいは電子的に発行・譲渡・割引が可能で、インターネット経由で利用できるため、手形に比べて印紙税や管理の負担を軽減できるメリットがあります。
一方で、利用には金融機関を通じたシステム登録や手数料が発生し、導入には一定のコストがかかるのが特徴です。これに対して期日現金は、単に振込で決済するだけであり、でんさいのように資金化や譲渡といった機能はありません。
つまり、期日現金は現金払いのシンプルな形態、でんさいは流通性と利便性を持った電子的な債権と整理できます。でんさいは特に大企業や取引先が多い場合に効率的ですが、中小企業にとっては手数料や導入コストが負担となる場合があります。
両者の違いを理解したうえで、自社に最も適した決済手段を選びましょう。
期日現金の主なメリットを3つ紹介
期日現金は、従来の手形決済やでんさいと比べてシンプルで透明性の高い決済方法です。特に中小企業や個人事業主にとっては、資金繰りや管理コストの面で多くのメリットがあります。
手形の場合、発行や管理に手間とコストがかかり、不渡りのリスクも伴いますが、期日現金ではこうした負担がありません。また、支払条件が明確であるため、受け取る側は資金の予定を立てやすく、支払う側も支払い猶予によって手元資金に余裕を持てます。このように、双方にとって安心かつ効率的な取引を実現できるのが期日現金の魅力です。
ここでは、期日現金の具体的なメリットを3つに分けて詳しく解説します。
手形発行や管理が不要となり双方のコスト削減につながる
期日現金の最大のメリットのひとつは、手形のような有価証券を発行する必要がない点です。手形を利用する場合、印紙税や発行・管理コストがかかり、さらに銀行や金融機関を通じた取扱いに伴う手数料も発生します。特に取引件数が多い企業にとっては、このコストは決して小さくありません。
さらに、手形は不渡りや紛失といったリスク管理も必要で、事務担当者の負担が増える要因にもなります。その点、期日現金は単に決められた期日に銀行振込を行うだけで済むため、事務処理を大幅に簡素化できます。
結果として発行・管理にかかるコストを抑えられるだけでなく、受け取る側も手形管理の手間から解放されるため、双方にとって効率的です。事務作業の簡略化はミス防止にもつながり、中小企業においては人件費削減や管理の負担軽減という大きな効果をもたらします。
支払条件が明確になり資金繰りを計画的に管理できる
期日現金は、支払期日が契約段階で明確に定められているため、受け取る側にとって資金繰りの見通しを立てやすいのがメリットです。手形のように譲渡や割引による資金調達はできませんが、その分、シンプルに「いつ入金されるか」がわかるため、資金計画を立てやすいのです。
例えば、月末締め翌月末払いといった条件が明確であれば、売上と入金のタイミングを予測しやすく、支払いや投資の予定を計画的に進められます。特に中小企業や個人事業主では、現金の流れが経営の安定に直結するため、このメリットは非常に大きいといえます。
また、支払う側にとっても期日が確定しているため、いつまでに資金を用意すべきかが明確になり、資金繰りを組み立てやすくなるでしょう。双方にとって予測可能性が高まり、不要なトラブルを避けられるのが大きな強みです。
支払う側にとって資金繰りに余裕が生まれる
期日現金は、支払期日までに一定の猶予が与えられるため、支払う側にとって資金繰りに余裕を持たせられます。例えば、商品やサービスを仕入れた直後にすぐ現金を支払う必要があると、手元資金が一気に減少して運転資金の確保が難しくなることがあります。
しかし、期日現金であれば決められた支払期日までの間に売上を回収したり、資金を準備する時間を確保できるため、経営を安定させやすいのです。特にキャッシュフローの変動が大きい業種では、この猶予が経営判断や資金調達に大きな安心感をもたらします。
また、期日が明確に設定されているため、突発的な支払いに追われるリスクも少なく、計画的に資金を運用できます。支払う側にとっては、資金の呼吸を整える仕組みとして機能するため、日々の経営活動を安定させる重要な手段となるのです。
期日現金のデメリットについて解説
期日現金は、手形やでんさいと比べて手続きが簡単で管理コストを抑えられる一方、受け取る側にとっては注意すべきデメリットも存在します。最大の特徴は現金で決済されるというシンプルさですが、入金が支払期日まで行われないため、資金繰りに影響する可能性があります。
また、手形のように金融機関で割引して早期に現金化する手段がなく、必要な資金を前倒しで調達できない点も課題です。さらに、支払う側の事情によっては支払いが遅れる、または滞るリスクも残されており、受取り側の経営に大きな影響を与える場合があります。
期日現金を導入する際には、こうしたデメリットを理解したうえで、資金管理や取引先の信用調査などを徹底することが重要です。
それぞれ順に解説します。
受取り側は入金まで時間がかかり資金繰りが圧迫される
期日現金では、売上が発生しても支払期日まで入金が行われないため、受取り側はその間の資金繰りに苦慮することがあります。特に中小企業や個人事業主は、仕入れや人件費、家賃などの支払いが毎月発生するため、入金の遅れがそのまま資金不足につながる可能性があります。
例えば、月末締め翌月末払いという条件の場合、売上から入金まで最大で60日近い期間が空くケースもあり、その間は自社の手元資金でやりくりしなければなりません。これにより、急な支払いに対応できず、銀行融資や短期借入を余儀なくされることも少なくないでしょう。期日現金は入金日が確定しているという安心感はあるものの、入金までの待期期間が資金繰りのプレッシャーとなる点は、受取り側にとって大きなデメリットといえます。
期日現金は手形のように割引や譲渡で早期現金化できない
手形であれば、金融機関で割引を行うことで期日前に現金化でき、必要に応じて資金を前倒しで確保することが可能です。しかし、期日現金ではこうした仕組みが存在せず、基本的に支払期日まで入金を待つしかありません。
そのため、急に資金が必要になった場合や、大口の支払いに備える必要がある場合には不便さを感じるでしょう。また、期日現金は手形やでんさいのように譲渡性がないため、他の取引先に対して支払手段として活用できません。
つまり、期日現金は現金が振り込まれるまで資金を動かせないという制約があり、資金調達の柔軟性に欠けるのです。この点は資金繰りがタイトな企業にとってはリスクとなり、場合によっては外部のファクタリングや短期融資といった補完的な資金調達手段を検討せざるを得ません。
期日現金は支払遅延など回収リスクに十分な注意が必要
期日現金は期日に現金で支払われるという前提の取引ですが、支払う側の資金繰りが悪化すれば、期日に遅延する、あるいは支払いが実行されないといったリスクが発生します。手形の場合、不渡りを出せば取引停止処分など法的な制裁があるため抑止力が働きますが、期日現金にはそうした強制力が弱く、回収リスクが比較的高いです。
実務では支払遅延が続けば取引関係自体に支障をきたし、経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、期日現金を採用する場合は、取引先の信用調査や支払履歴の確認を徹底し、必要に応じて契約条件を文書で明確に定めることが不可欠です。
さらに、回収不能のリスクを見込んで貸倒引当金を計上するなど、会計処理でリスクを織り込む工夫も必要です。期日現金は便利な反面、回収リスクに敏感であることを忘れてはいけません。
実務における期日現金の活用方法と資金繰り改善の工夫
期日現金は、手形の発行や管理が不要でシンプルに運用できる一方、入金までの期間に資金が動かせないという課題もあります。そのため、実務では資金繰りを安定させる工夫や補完的な資金調達手段との併用が欠かせません。
中小企業や個人事業主では、日々の仕入れや人件費などの支払いに対応するため、入金予定を正確に把握することや、場合によってはファクタリングなどの外部サービスを活用する必要が出てきます。これにより、期日現金のメリットを活かしつつ、資金繰りのリスクを軽減できるのです。
以下では、実務における期日現金の活用方法と資金繰り改善の工夫を解説します。
期日現金と併用できるファクタリングによる資金繰り改善
期日現金は決められた日に必ず現金が振り込まれる仕組みですが、受け取るまでの期間が長いと資金ショートのリスクが発生します。そこで有効な手段がファクタリングです。ファクタリングを活用すれば、期日現金の売掛金を譲渡して早期に資金化でき、仕入れや人件費、急な支払いにも対応しやすいです。
2社間ファクタリングを利用すれば取引先に知られずに資金調達が可能で、信頼関係を損なう心配も少なくなります。また、金融庁や中小企業庁もファクタリングを資金調達の一手段として紹介しており、中小企業が短期資金を確保する際の実務的な選択肢になっています。
併用してファクタリング利用を考えている方は「オンラインファクタリング・Web完結17選!非対面のサービスを紹介」、「ファクタリング会社おすすめ20選!優良サービスを紹介」の記事もご確認ください。
さらに、取引先の信用不安に備えて回収リスクを回避する手段としても有効です。ただし、ファクタリングには手数料が発生するため、相場を比較して適正な業者を選ぶことが大切です。期日現金とファクタリングを組み合わせれば、資金繰りを柔軟にコントロールし、経営の安定性を高められます。
期日現金の入金予定日を管理して資金繰りを安定させる
期日現金を利用する際には、いつ売掛金が入金されるのかを正確に管理することが資金繰りの安定に直結します。入金予定日を把握せずに仕入れや支払いを進めてしまうと、キャッシュ不足に陥り、資金ショートを引き起こす恐れがあります。
そのため、実務では売掛金の期日を一覧化し、月ごとの資金収支計画に組み込むことが重要です。会計ソフトやクラウド会計システムを利用すれば、期日管理を自動化でき、入金予定と支払い予定のズレを早期に把握できます。
また、金融庁の「中小企業金融円滑化法」の関連指針でも、資金繰り表の作成と管理の重要性が強調されています。資金繰り表を用いれば、期日現金の入金予定日をベースに資金の流れを可視化でき、支払期日と入金期日のギャップを事前に確認可能です。
これにより、不足が予測される場合は融資やファクタリングなどを検討する余地が生まれ、経営リスクを低減できます。さらに、入金予定日を基準に経費や設備投資を調整することで、無理のない資金計画を立てることが可能になります。
期日現金の強みを最大限活かすためには、入金予定日を徹底的に管理して資金繰りを先読みする姿勢が欠かせません。
期日現金取引における会計処理と仕訳の流れ
期日現金は掛け取引の一種であり、取引発生から実際の入金までに一定のタイムラグがあるため、会計処理においては正確な売掛金の計上と入金処理が欠かせません。
一般的には商品やサービスを提供した時点で売上を計上し、同時に売掛金を認識します。その後、決められた期日に現金振込が行われた時点で売掛金を消し込み、現金または預金として処理。会計処理の流れを正しく理解しておかないと、資金繰りや決算数値にズレが生じる可能性があります。
特に中小企業では、入金予定と支払予定のタイミングを誤ることでキャッシュフローが悪化するケースも多いため注意が必要です。また、売掛金は未回収リスクを伴うため、貸倒引当金の設定を行い、将来的な損失に備えることも重要です。
経理担当者は「売掛金の計上 → 入金処理 → 回収不能リスクへの対応」という一連の流れを体系的に管理すると、正確な会計処理と健全な資金管理を両立できます。
売掛金計上から入金までの仕訳例
期日現金取引の仕訳は、売上発生から入金までの流れを段階的に記録する必要があります。以下に基本的な仕訳例を示します。
(借方)売掛金 1,000,000円
(貸方)売上 1,000,000円
上記の時点では代金がまだ入金されていないため、売掛金として資産計上します。
(借方)普通預金 1,000,000円
(貸方)売掛金 1,000,000円
上記の仕訳で売掛金が消込まれ、現金化されたことを反映します。実務では消費税の区分や振込手数料の控除なども考慮する必要があるのです。
例えば、振込手数料が差し引かれて入金される場合は「支払手数料」として仕訳を追加します。また、期日現金の場合は売掛金の入金期日を資金繰り表に反映させておくことが不可欠です。
入金予定と支払い予定をリンクさせて管理することで、資金ショートを防止し、健全なキャッシュフローを維持できます。
貸倒引当金などリスクを見込む処理
期日現金は決められた日に入金される前提で運用されますが、実務上は取引先の経営状況や資金繰りの悪化によって支払いが遅延または不能になるリスクが存在します。そのため、企業会計原則や企業会計基準に基づき、売掛金には貸倒引当金を設定することが推奨されています。
貸倒引当金とは、将来的に発生する可能性のある貸倒損失に備えるため、あらかじめ損金として計上しておく会計処理です。例えば、売掛金残高が1,000万円あり、過去の実績から1%程度の貸倒が見込まれる場合には、以下の仕訳を行います。
| (借方)貸倒引当金繰入 100,000円 (貸方)貸倒引当金 100,000円 |
上記のようにすることで、実際に貸倒が発生した際には貸倒引当金を取り崩すだけで済み、決算への影響を最小限に抑えられます。期日現金では手形割引のような早期現金化ができないという特性があるため、回収リスク管理は必須です。
経理担当者は、期日現金の利便性とともに、リスクへの備えもバランスよく実施することが求められます。
期日現金に関わる法規制と実務で注意すべきポイント
期日現金は手形の代替手段として近年利用が広がっていますが、単なる決済方法の違いにとどまらず、法規制や契約実務においても重要な位置を占めています。特に中小企業が大企業に商品やサービスを提供する場合には「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が適用され、支払サイトの長期化や不当な条件変更が禁止されています。
さらに、手形から期日現金への切替えを行う際には、契約内容の明確化や支払期日遵守の仕組みを整備することが不可欠です。こうした法的枠組みを理解せずに取引を進めてしまうと、下請法違反や債権回収トラブルに発展する可能性があり、経営リスクが高まります。
ここでは、下請法における期日現金の位置付けと、手形から切替える際に注意すべき契約上のポイントについて解説します。
下請法における期日現金の位置付けと実務での取扱い
下請法では、親事業者が下請事業者に対して商品やサービスを提供させた場合、支払期日を「給付を受けた日から60日以内」に定める必要があると規定しています。
下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつできる限り短い期間内に定める義務。
引用:中小企業庁「下請代金支払遅延等防止法」
つまり、期日現金を利用する場合も、この法律に基づいて適切な支払サイトを設定しなければなりません。支払期日が60日を超えるような契約は、下請法違反として行政指導や罰則の対象になる可能性があります。
実務上は、発注企業と受注企業の双方で「起算日をいつとするか」を契約書に明記し、サイトが適正か確認してください。
また、期日現金は手形と異なり譲渡や割引による早期現金化ができないため、下請企業側の資金繰りに不利にならないよう、支払条件の妥当性を十分に検討する必要があります。さらに、金融機関や取引信用保険を活用して、万が一の遅延や不履行リスクに備えることも実務的な対策として有効です。
手形から期日現金へ切替える際に必要な契約上の注意点
手形決済から期日現金へ切替える際には、取引先との契約条件を改めて見直す必要があります。手形は受取人が金融機関に割引に出すことで早期に現金化できる一方、期日現金は入金期日まで現金化できないため、資金繰りへの影響が異なります。
そのため、切替えの際には「支払期日の設定」「支払方法(銀行振込等)の明確化」「遅延が発生した場合の対応」を契約書に明記することが必須です。
また、経済産業省は「中小企業取引条件改善に関する指針」において、長期的な支払サイトが中小企業の経営を圧迫している点を指摘しており、期日現金を導入する場合も支払条件の適正化を求めています。特に取引先が大企業の場合、下請法の規制に沿った支払サイトを遵守しているかを必ず確認しなければなりません。
実務的には、契約変更の際に「前倒し支払の可能性」「部分払いの有無」「ファクタリング等の資金繰り手段を利用できるか」といった補足条件を取り決めることで、受注企業の資金繰りリスクを軽減できます。
期日現金はシンプルな仕組みでありながら、契約内容次第で受注側に大きな負担がかかる可能性があるため、法規制と実務慣行の両面から入念に確認しましょう。
期日現金を導入する際に検討すべき実務上のポイント
期日現金はシンプルで管理しやすい決済方法として注目されていますが、導入には一定のリスクも伴います。特に、取引先の信用状況や支払能力を十分に確認せずに利用すると、支払遅延や回収不能といったトラブルに発展する可能性があります。
また、契約条件を曖昧にしたまま進めてしまうと、双方で解釈の食い違いが生じ、紛争につながる恐れも。さらに、自社の資金繰りや経営状況に応じて、期日現金を採用すべきかどうかを判断することも重要です。
ここでは、期日現金を導入する際に必ず検討しておきたい3つのポイントを解説します。
期日現金導入で取引先の信用力を実績などで確認しておく
期日現金は、支払期日まで代金を現金で受け取れないため、取引先の信用力が直接的にリスク管理に関わります。したがって導入前には、相手先の財務状況や過去の支払実績を入念に調査しておく必要があります。
信用調査会社のレポートを活用したり、取引先の決算書を確認することにより、健全な資金繰りを行っているかを見極めることが可能です。過去に支払遅延が頻発している取引先や、業績が急激に悪化している企業に対しては、期日現金よりも前払いや保証付きの取引を検討するほうが安全です。
加えて、複数の取引先とバランスよく契約を行い、依存度を下げることでリスクを分散できます。信用調査や実績確認を怠ると、期日現金の利便性が一転して資金繰りリスクにつながるため、初期段階での徹底した確認が欠かせません。
契約条件を明確に定めてリスク管理を徹底する
期日現金を導入する際には、契約書において支払期日や起算日の取り決めを明確にしておくことが不可欠です。何日締めで翌何日払い等の表記を曖昧にすると、解釈の違いから支払遅延や紛争の原因になります。
また、契約条件には「支払が遅延した場合の利息や違約金」「支払不能に陥った場合の取扱い」など、トラブル発生時の対応方法を盛り込んでおくことが重要です。さらに、電子契約やクラウド管理システムを活用し、契約条件の透明性を高め、監査や内部統制にも対応しやすくなります。
実務では、契約書に支払サイトや入金手続きの方法を細かく記載し、双方が共通の理解を持てるようにすることが肝心です。徹底したリスク管理により、期日現金のメリットを享受しながら安全に運用できます。
自社の経営状況に合わせた期日現金の運用可否を検討する
期日現金を導入するかどうかは、自社の経営状況や資金繰りに大きく依存します。例えば、売掛金の入金までに余裕を持った運転資金が確保できている企業であれば、期日現金の導入は支払条件の明確化や管理コストの削減につながる有効な選択肢となります。
しかし、常に資金繰りが逼迫している企業や、外部からの借入に依存している企業では、入金までの待期期間が資金繰り悪化のリスクを高める可能性も考えられるでしょう。そのため、自社のキャッシュフローを分析し、売上・仕入れ・人件費・税金などの支払予定と照らし合わせて、期日現金の導入が現実的かどうかを判断してください。
また、資金繰りが厳しい場合には、ファクタリングなど早期資金化できるサービスと併用することも検討すべきです。公的機関の支援制度(例:日本政策金融公庫の資金繰り支援策)を併用するのも一つの手です。
経営環境や取引の特性に応じた柔軟な判断を行うと、期日現金を無理なく取り入れられるでしょう。